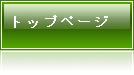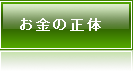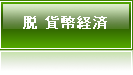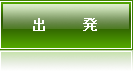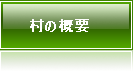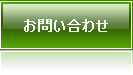共産主義下における貨幣経済
BRICsという近年、台頭が著しい新興経済発展諸国がある。
BRICsとは、ブラジル・ロシア・インド・中国を総称した呼称である。
中でも中国は、特に著しい発展を遂げている。その中国国内で今、一体何が起きているのか?
中国は、共産主義の国である。
そもそも共産主義とは、すべての財産を共有するという思想のもとに考えられた社会制度である。
その制度のもとでは、貨幣そのものは存在していても、統制経済であるがゆえに
本来貨幣経済がもつ「競争原理」が働かないために経済発展することはなかった。
長い間共産主義を貫いてきた中国も、鄧小平以後
「豊かになれるものから豊かになろう」をスローガンに、共産主義下における非効率な経済のあり方を改め
本来の貨幣経済をようやく導入し始めた。
中国は、世界一の人口を有する国である。
その中国が一旦貨幣経済を推し進めることになれば、めざましい発展を遂げるだろうことは
20年以上も前から欧米の著名な経済学者たちは、予測していた。
その予測どおり現在では、最貧国であった中国が日本を抜き世界第二位の経済大国にまでなった。
そして、中国はいずれアメリカを抜き世界一の経済大国になるかもしれない。
その世界一の経済大国になろうとしている中国国内で、今、猛烈な勢いで二極化が進んでいる。
インターネットで閲覧できるフリー百科事典のウィキペディアには、中国は
「経済の開放を強力に推し進めた結果、全国民の0.4%が国民所得の70%を占有するようになり年々格差が拡大し続けている。」
と記されている。
全国民のたったの0.4%が国民所得の70%を占めているというのである。
これはもう異常ともいえるほどに二極化が進んでしまっている状態だ。
一体、これはどういうことなのだろうか?
経済大国になったはずの中国で、なぜ急激に「富めるものと貧しいもの」の二極化が進んでいるのか?
共産主義下においても、やはり貨幣経済の行く末は、二極化しかないのか?
工場における機械化やオフィスでのコンピューター化がまだ進んでいなかった時代においては
そこで働く熟練工場労働者や専門知識を持つ事務職員や営業マンは、たくさん必要だった。
ところが、現代では効率化を最優先する貨幣経済下で発明された「機械」や「コンピューター」が
皮肉なことに人間の職場を奪ってしまったのだ。
現代は、高度経済成長期に私たちが経験してきたような貨幣経済では、もはやないのである。
一部の資本家や経営者と、あとは末端で働く、かろうじて人間しかできない単純労働者だけいることこそが
貨幣経済における究極の効率化となってしまったのである。
中国においても、しかりである。すでに機械もコンピューターもありきのところからの出発だったのである。
熟練した工場労働者も専門知識を持つ事務職や営業マンも必要ないところからの出発だったのである。
であれば、急激な経済成長とともに、急激な二極化が進むことは当然のことである。
「いやいや、中国が経済発展した理由は、安い労働力があったからだ。」といわれるかもしれない。
確かに、その通りで、安い労働力があったからこそ世界の工場ともいわれるほどに
たくさんの工場ができ、たくさんの工場労働者を生み出し、たくさんの製品を作り出し、経済発展したのも事実である。
しかし、思い出していただきたい。
私たちも高度経済成長期、日本は世界の工場といわれ、戦後何十年と経済成長を続けてきた。
今、中国は私たち日本人が通ってきた道をその何倍もの速さで経験し
貨幣経済の威力、魔力、絶大さ・・・を実感しているのである。
そして、中国でもやはり、一部の特権階級ともいえる富裕層と低賃金で働く貧困層の二極化が
すさまじい勢いで進んでいるのである。
共産主義社会であっても、貨幣経済下においては、同じように二極化は進むのである。
同様にロシアでもまた、二極化が進んでいることは、周知の事実なのだ。
ここでも、また、貨幣経済の行く末は二極化を示しているのか?・・・・・・